TURN EX:7/7 「その願いは」 零式彗星/千年王国
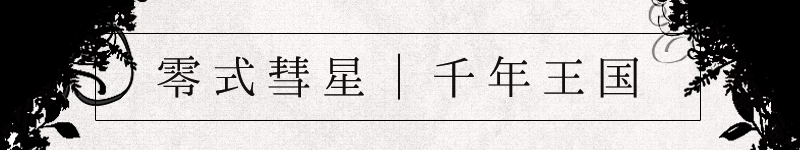
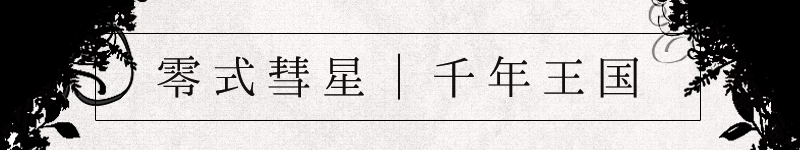
「『タナバタ』?」
「そう、七夕!」
エトリア、長鳴鶏の宿。5人部屋に戻り防具を解いていたリザンに、彼らの部屋に飛び込んできた少女は笑顔で言い放った。
栗色のつやつやしたおかっぱ髪を揺らし、びし、と彼にひとさし指を突きつける。
「ジパングに昔からある風習でね、『笹に願いをつづった短冊をむすび星空に掲げると、願いがかなう』の。ってことで、はいこれ。書いてね」
極東の国ジパング出身だという桃色着物に紫袴のブシドーの少女ルリは、椅子に座り話を聞くリザンに青の細長い紙切れを渡し、笑みという名の無言の圧力をひとつ。
「シェズくんも、はい。なんでもいいけど、願いはひとつだけね」
リザンの返事を待たぬまま、部屋の隅の窓際で読書していたシェズのところに歩み寄ったルリ――「くん」付けしているが、17歳のルリ嬢よりもシェズは2つ年上だ――は、有無を言わさず空色の紙切れを渡す。
相変わらずの無表情だったが、それを受け取りルリの笑顔を見上げたシェズは、少し困っているようにリザンには見えた。
「よし、っと」
シェズが受け取ったことに満足したのか、髪に飾った花かんざしにも劣らぬ可憐な笑顔でルリは部屋の入り口まで軽い足取りで戻った。
いつも笑顔という娘ではないので、今日はよほど機嫌がいいのだろう。
くるっと着物のすそをひるがえしてふり返り、小首をかしげてリザンに問う。
「それで、あとの3人はどこ?」
同ギルドの一軍メンバーだ、帰還後の行き先を知っているだろうと思われるのは当然だ。
普通、ならば。
「ああ、それぞれ用があるみたいだよ」
爽やかにリザンは返事をしたが、内心では明言を避けていた。
彼なりに3人がどこにいるかおおよその推測はつくものの、まだ出会ってから日が浅いため、ルリに教えられるほどの確信はない。
追求されたらどう答えようかと思案していたが、上機嫌のルリ嬢はあっさりと納得した。
「そう? なら、探すしかないわね。よしっ、いくわよナル!」
勢いよく廊下へ飛び出すと、兄の名をひと呼びしてブシドー乙女はどこかへ行ってしまった。
「おいこら、ルリ」
呼ばれた双子の兄、ナルの呆れた声が廊下から聞こえる。金の短い髪をしたパラディンの青年が戸口に姿を見せて、部屋の二人へと頭を下げた。
「すみません」
「いや、謝ることじゃないさ。こういうのも、悪くないだろう」
ただでさえ雰囲気のよくない滑り出しの一軍だ。参加できる状態じゃなくとも、こうしたイベントを呼びかけてもらったほうが少しは和むかもしれない。リザンは本心から微笑んだが、
「いえ、その紙切れです」
若きパラディン、ナル青年の顔は曇っていた。
「ん? 普通の紙じゃないのか?」
「はい。それは一枚ずつ、カースメーカーのティーによる認識呪法が施されてます。明日の朝ルリが笹を回収する際に、短冊をかけていなかった人が誰なのかすぐわかるように」
「……? そうか」
それが別段悪いことのように思わないリザンは、頷くが。
「ルリいわく『参加しなかったひとは、首討ちの練習の刑なんだ☆』と」
静かに妹の口調をモノマネして告げる(しかも声音まで似ている)ナルの目は、しかし冗談を言っている光ではなかった。
「……。 そうか」
できるだけ爽やかにリザンは返事をしたつもりだが、困ったことになったと思っていた。
ブシドーの『首討ち』といえば、刀を使った一撃必殺の技としてリザンも聞き及んだことがあるほど名高い。とても威力の高い、そして危険な刀術だ。
くわえてルリ嬢のレベルは40近いが、今日の初樹海でリザンたちが上がったレベルは、7。
練習だけでも洒落にならない。間違いない。
しかし、ここにいる2人はいいとして、あの3人は『願い事を書く』だろうか。
特に、それぞれ穏やかでない心境であろう、あの2人は。
「適当でもいいんで、なにか書いて宿の裏手にある笹につるして下さい。匿名で構いません」
「わかった。俺たちは善処するよ」
この青年は一見すると妹に振り回されているように見えるが、その実しっかりと手綱を締めており、聡い人物だ。この兄妹を何度か見たリザンはそう思っていた。
初の樹海探索後にも関わらず、浮かれているわけでも興奮しているわけでもなく、さらにメンバー5人のうち3人がいないという事態。「俺たちは善処する」、と言った意味。
これらを、上手く読み取ってくれるとありがたい。
リザンの意図に気付いたのか、ナルは真摯に頷いた。
「首討ちは俺が阻止します。それじゃ。お疲れ様です、お二人とも」
正式な敬礼をひとつ深々として、金髪の聖騎士は去っていった。
お疲れ様です、といった彼の言葉にはいたわりが滲んでいた。この状況を欠片でも察してくれたのだろう。リザンはひとつ安堵の息を吐いた。
「…………」
廊下を見ていたリザンは、後ろに視線を感じた。振り返って一瞬目が合った柘榴色の瞳はとても心配そうな色をしていたが、次の瞬間、いつもの無表情に戻る。
一瞬かいま見たシェズのその感情に、リザンは思う。
(上手くかみ合えば、息が合うと思うんだけどな俺たち)
リザンはこの一軍メンバーは悪くないと思っていた。個々にしがらみは抱えているようだが、根底にある彼らの意思は、中途半端なものではない。
むしろ、自分の志はぬるかったとすら思うことがある。
(……共に戦うというのは、思っていた以上に難しいものなんだな)
そんな感想を思い、リザンは本に目を移したシェズに微笑みながら問いかけた。
「読書もいいが、書かないと大変な目にあうぞ、シェズ。 これも一種の戦場じゃないかな」
最後の「戦場」という言葉に納得したのか、シェズはぱたりと本を閉じ、歩み寄ったリザンが差し出した
ペンを受け取った。
「…………ええっと……」
それから数時間が過ぎた、夕刻。
「お帰り、フレアロット」
笹の前で赤色の紙を手に立ち尽くしている木苺の髪の少年を通りすがりに見かけたリザンは、穏やかに声をかけた。
びく、と身じろいだのが傍目にもわかるほど驚いて、彼は振り返る。
「あ、リザンさん……。 た、ただいまです……」
所在なさげに視線を落としながら、弱い声で返事をする。
……わかりやすい。
リザンはうなだれたフレアロットのそばまで歩み寄ると、その柔らかい巻き毛の頭をぽんぽんと優しく叩いた。
「今日は初日だ。上手くいかなくても仕方ないさ」
「……お気遣い、ありがとうございます。けど、そういう問題じゃ……ないと、思います」
お礼と共に頭を下げるときは目を上げたが、辛そうに顔をしかめ、フレアロットはまた地面に緑の瞳を落とした。
彼が口にした暴言が相手にとってどんなものか。もし、そのすべてを理解できてはいなかったとしても、自分の行動に非を認めて落ち込む素直さは長所だとリザンは思う。
「気にするなら、ヘヴンリィに謝るんだな」
「………………、はい」
なにかまだ思うところがあったようだが、逡巡したのち、フレアロットは頷いた。
フレアロットの言葉もまずかったが、それまでのヘヴンリィの態度もそれと同等くらいに悪かっただろう、とリザンは思っている。
反省はいいことだが、フレアロットが100%自分のせいだと思うのも、あまりよろしくない。逡巡する反抗心があるくらいがちょうどいい。
「で、フレアロットも書いたんだな。短冊」
「……はい、書かないと首討ちだといわれたので」
フレアロットが差し出すその紙にかかれた一文を見て、ああ、とリザンは納得した。
彼はやはり、聖騎士だ。
真っ先に剣をふるうその無謀ともいえる戦い方に反し、その表情は好戦的ではなかった。きっと彼なりの理由があるのだろうと思い、リザンはすすんで前へ出ようとはしなかった。
見込み違いではなかったことに、ふっとやわらかく笑みをこぼす。そして、短冊をその手からさらった。
「あ」
目を丸くしたものの、抵抗しなかったフレアロットに背を向けて、リザンは笹の一番上……頭ひとつ小さいフレアロットの身長では届かなかったところに短冊をかけた。
「どうせつるすなら、高いほうがいいだろう?」
「……ですね。ありがとうございます」
『より高いところにかけたほうが、願いがかなう』。
リザンは午後に会ったエンジとミズキにそう聞いていたが、知らないふりをして爽やかに笑った。
「…………」
金鹿の酒場で夕飯をとったあと、笹を見に来たリザンはその下に佇む人影と、舌打ちを聞いた。
アッシュブラウンのはねた前髪が、窓からこぼれる宿の灯りに照らされて煌めいている。
「遅かったな。ヘヴンリィ」
「……リザンか」
硬い声。彼は振り返らなかった。
未だに怒っているのだろうか。……仕方ないといえば仕方ない。
私服の黒いコートを着ているということは、おそらく夕飯に行った4人と入れ違いに部屋へ戻ってきたのだろう。
フレアロットの短冊の心配がなくなり、ブレスも「短冊、どうした?」と夕飯の席で聞いたらひとつ頷いたため、無事に笹へかけたと思われた。
残るは彼の短冊だけだった。白い紙切れを手にしているのを認め、ほっとする。
しかし、ヘヴンリィはその紙を握りつぶし、ぽいとぞんざいに投げた。
ぱさりと地面に落ちるのも見ず、彼はこちらに振り向き――つまり笹に背を向け、顔をしかめてリザンの横を通り過ぎようとする。
すれちがいざまに肩を掴んでその場に押しとどめるが、彼はリザンのほうを見なかった。
「離せよ」
「待て、ヘヴンリィ。書いたんだろう? 飾らないと、首討ちだぞ」
「望むところだ」
かたくなに拒否を貫くヘヴンリィの横顔に、リザンはいぶかしんだ。
フレアロットが来る三日前まで、饒舌とはいえないまでも、リザンは彼とそれなりに話してきた。
艶のある紫の瞳が印象的な顔立ちをわざと崩していると思われる不機嫌顔と黒い服装に反し、彼はとっつきにくい人物ではない。
フレアロットには毒を吐いているが、初対面からあの二人は最悪だった。あれは例外だ。
例外でなけば、彼は聞かれたことには答えるし、話したくないことは態度でそう告げる。
警戒心からなのだろう、ギルドのメンバーに対してもよそよそしい空気を保ってはいるものの、闇雲に心配を拒否するほど他人を無碍にする青年ではないと思っている。
なにか理由があるのだろうが、先の樹海での一件とはなにか違う気がして、リザンは静かに言った。
「お前がよくても、俺たちはよくない。 お前が首討ちにあうのは困る」
言葉の途中で、首討ちなどに遭ったらたやすく切り崩されそうな線の細い肩から手を離し、リザンは投げ捨てられた白い紙まで歩み寄る。
そしてその紙を拾い上げ、そっと広げた。
「……っ、おい、他人が書いたやつを勝手に見んじゃねーよ……! 匿名だろそれ!」
とがめるようなヘヴンリィの声が背にふりかかるが、リザンはそれすらほほえましく聞こえた。
(やはり、息が合えば悪くないんじゃないかな。俺たち)
微笑しつつその紙のしわを指で直すと、リザンは笹の一番上……ヘヴンリィが見上げて舌打ちしていたと思われるもののとなりへ、その白い紙をかける。
「まて、そこは……」
珍しく焦ったようなその声に、ひもを笹へと結わき終えたリザンは振り返り、爽やかに笑った。
「どうせつるすなら、高いほうがいいだろう?」
「…………」
複雑な顔をしていたヘヴンリィは、眉の縦じわがいつもより少し緩和されていた。
いつもの不機嫌顔よりは、困っているほうが幾分悪くない。
(笑ったら、もっといいんだろうけどな)
故郷でさまざまな美男美女を目にしてきたリザンだったが、彼の顔立ちはとりわけ綺麗だと思っていた。それだけに、不機嫌な表情をさせているのは、勿体無いと思っている。
しかし、特にその気のないリザンが綺麗だと思うくらいなのだから……きっと、彼の態度も不機嫌顔も、警戒心も、彼の理由があるのだろう。
けれど、彼ら『グランドクロス』の一軍は始まったばかりだ。おそらく、先は長い。
そして、この一軍は彼が警戒するような者たちじゃない。
共に戦う限り、いつか彼も笑えるようになるだろう。……そうできたらいいと、リザンは思った。
「さ、部屋に戻ろうか。ヘヴンリィ」
「…………ちっ」
横に歩を進めて問いかけたリザンに、ヘヴンリィは舌打ちを返す。だが、笹をどうにかする訳でもなく、彼はそのままリザンの数歩後ろをついてきた。
「……同じ願いをつるす必要なんか、ねえだろうが」
すねるようにひとりごちたヘヴンリィの小声を聞いてしまい、リザンはそっと苦笑した。
(その願いが誰のものか知ったら、きっとそんな口も叩けないぞ、ヘヴンリィ?)
赤い紙と、白い紙。そこに書かれた願いは、ひとつ。
『誰も倒れませんように』。
あの気まぐれブシドー乙女、ルリ嬢のただの思いつきだったとしても、七夕は良いイベントだった。
天の川がきらめく星空を見上げながら、リザンはそう思う。
明日も、問題だらけの一軍は、それでも迷宮に潜れそうだった。