TURN3 「彼の理由」 零式彗星/千年王国
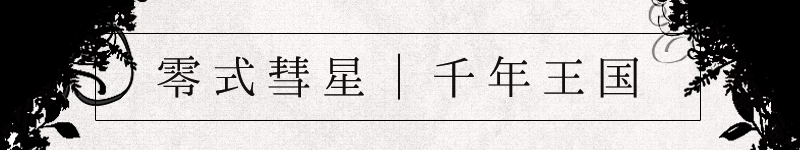
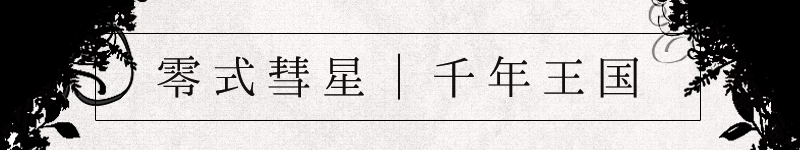
(……最悪だ!)
長い指が、黄色い花とやわらかい葉を丁寧に手折る。
後ろでひとつに束ねていたアッシュブラウンの髪が、ひとすじこぼれてしろい頬にかかる。
深い紫水晶(アメジスト)色の瞳で、彼はそれを一瞥。
白磁のような肌に、髪と同色の細身の眉と、長い睫毛。色素の薄いそれらは、瞳の色をいっそう際立たせている。
こぼれた髪をかきあげようとした彼は、指先が草汁で緑に染まっているのを思い出し、桜色の形の良い唇でちっ、と舌打ちをひとつ。邪魔な髪をそのままにして、再び花々へと目を落とした。
天使を模した背の飾り羽が白く高貴なエンジェルローブをまとい、彼は花を摘む。
整った甘い造作と相まって、その光景は本当に天使が降り立ったかのように、とても綺麗だ。
ただし――
(ざけんじゃねえぞあの野郎!)
その表情が、鬼神もかくやの怒り全開な形相でなければ、の話。
人影のない緑の丘で、優美なローブの袖を無造作にまくり、彼はひたすら花を摘みまくっていた。
緑鮮やかな樹海の入り口から、すこし歩いたところの傾斜には無数の野草が群生している。
彼……ヘヴンリィが摘んでいる、黄色い小花をつける野草は大ぶりな籐の籠に可愛らしくおさまっているが、れっきとした薬の材料だ。セントジョンズワート。抗炎症剤、消毒剤になる。
しばらく黙々と作業を続けていたが、風がひとすじ吹いて髪が目にかかり、手を止める。
ふう、と息をついて籠をのぞくと、両手で抱えてもあまるほどの花があふれていた。
小さい花にもかかわらず、その様は大きな花束のようだ。
もういいか、と呟いた彼は、アザミのようなほの赤い花弁の草を摘み始めた。
ホーリーシスル。傷の回復力を高める効果がある。
ヘヴンリィの医術式は、こうした薬草を主とした薬品を媒体にし、自身の魔力と合わせた治癒医術式を負傷者へ開放するもの。
純粋に医薬品を使って医術式を発動するやり方も学んだが、薬草から自作した薬のほうが魔力との相性が良かったため、エトリアに来て以来、ときどきここへ来て薬草を摘んでいた。
群れるのを苦手としている彼は、一人になれる時間がとれるので都合がいい、とも思っていた。
今日は薬がかなり減ったため、補充をしなくてはいけないというのもある。
帰りは遅くなる、と彼はブレスに告げておいてある。
できればいっそ帰りたくないが、それは叶わない希望だった。
今エトリアは冒険者であふれており、圧倒的に宿屋が足りていない。
一部屋に5人つめこまれているとはいえ、樹海ビギナーの彼らが部屋を借りられているのは奇跡に近い。元一軍の英雄たちが宿のひとと顔馴染みのため、無理を言って借してもらっているらしい。
どこかで一人で宿を取るには相当な金額を積まないといけないが、祖父の仕送りとケフト施薬院の手伝いで食いつないでいる彼には、そんな金銭的余裕もない。
夕飯までは別行動できるにしても、夜には戻らなければならなかった。
(どっかで飲んで夜中に帰るか……いや、摘んだ分調合しねーとならないんだよな)
手折った草はすぐに傷む。乾燥させると媒体反応が鈍くなるため、その日のうちに、アルコールや香油などと合わせて調合をしておかないといけない。
その手間を考えると、夕飯どころかむしろ早めに帰ったほうがいいくらいなのだが……
顔をあわせたくない。
命知らずな戦い方をしている上に、「メディックなんだから、傷を治すのは当然だろう?」とかのたまいやがった、あいつとは。
その傷を見たやつがどう思っているかなど、あいつは考えていないのだろう。
どんな思いで怪我の治癒をしているかなど、知らないくせに。
……腹がたつ。 どこまでも。
(ああくそっ、あいつがどっか出てろよ! むしろ、どっか行ったまま帰ってくんな!!)
ホーリーシスルは茎が丈夫なので、彼はその草をぶちぶちと乱暴にむしっていた。
そんな彼の耳に、聞きなれない声が不意に割り込んできた。
「ちょっとー」
「そこのお兄さーん」
声音は低めで低調だが、テンポだけは絶妙なその声。
「……え?」
少々間抜けな声と共にヘヴンリィが振り向くと、ギルドの先輩二人が立っていた。
ひとりは、右の褐色銀髪金眼ダークハンター。右目下に泣きボクロをもつ双子の弟、ミズキ。
ひとりは、左の白肌金髪碧眼アルケミスト。左目下に泣きボクロをもつ双子の兄、エンジ。
色は全部異なっているが、そのつくりはどこまでも良く似ていた。
凡庸な中肉中背で、ほがらかだがどこか食えない笑顔は猫を思わせる。
……なんで、彼らがここに?
「『突撃☆新一軍インタビュウ♪』第三回目は、メディックのヘヴンリィ氏や!」
「緑の丘とエンジェルローブ。いやぁ実に絵になりますわー。カメラはん、ここはアップで激写やぞっ」
唐突に現れた先輩双子コンビは、笑顔で訳のわからないことを明後日の方向へ解説しはじめた。
二軍の探索が忙しいようで、軽く挨拶を交わしたときしか会話していなかったが、見かけている印象では彼らはいつもこんな調子だ。
聞いている分には面白い人たちだとヘヴンリィは思っていたが、からまれると、ちょっと戸惑う。
「……誰に向かって喋ってるんですか。エンジさん、ミズキさん」
無視するのも何なので、ヘヴンリィはとりあえず素朴な指摘をしてみることにした。先輩のうえに年上なので、敬語で。
「ああっと、一軍ともあろう人がカメラ目線も知らんようですよ!」
「うむ、これは由々しき事態や。俺の氷結の術式で、熱い制裁をぶちかますべきやろか」
「……あの、氷結の術式は熱くないんじゃ。それにカメラもないし」
「お、ローテンションながらツッコミは的確やぞ。ミズキ」
「そやね、エンジ兄! プラス1000点やっ」
「……1000点って何基準ですか。っつーか、『第三回目』ってことは、オレは三番目ですよね?」
疑問点は多々あれど、ヘヴンリィは気になる箇所だけを聞いてみる。
「おおっ、今回のゲストは鋭いで! さすがテンちゃんやわー」
「せやな、さすがはツッパリ凄腕ドクターのテンちゃんやっ」
二人はオーバーアクションで引きを表現し、ざざっと後ずさった。
聞いたことのない単語に、ヘヴンリィは怪訝そうに首を傾げる。
「……『テンちゃん』?」
双子ペースに気圧されているのか、「今回のゲストは鋭い」と「ツッパリ凄腕ドクター」のふたつのツッコミどころは、完全にスルー。
「そ。『ヘヴンリィ』って、和訳すると『天』やねん。せやから、テンちゃん」
「あ、嫌やった? 渾名にトラウマとかあったん?」
「……いや、べつに。っつーか、『和訳』って」
「なら、こっからはテンちゃんでいくでー!」
「おー、公認やでー!」
天然スルーにもめげず、難しいツッコミを即座にかき消し、先輩双子のテンションは無駄に上がる。
呆然と立ち尽くしつつ、ヘヴンリィはひかえめにもういちど聞いてみた。
「……まあいいですけど、一定方向の虚空と話すの止めませんか。それより、三番目……」
「おっ、そんな話もあったなぁ。テンちゃんの前は、ブレっちやった」
ミズキがこともなげに言った、その単語。予測がつくが……恐々と、問い返してみる。
「……『ブレっち』……??」
間髪いれず、エンジにばしっと背中を叩かれた。
「なーにとぼけとんねん、テンちゃんっ。ブレっちゆーたら、ブレス氏しかおらんやろ」
「面白かったなぁ、ブレっち♪」
(ぶ、ブレスが面白い……!? っつーか、よくそんな渾名つけられたな……!)
両隣でにこにこと語る双子の答えに、ヘヴンリィは唖然とした。
常にぴりぴりした空気をもち、冷めた表情の長身のレンジャー、ブレス。
寡黙でクールな態度も悪くはないと思うので、彼のことは嫌いじゃない。
ひとことも喋らないため、実は声が出せないのかもしれないと考えていたので、すこしほっとする。
しかし……冗談言うには怖い感じだし、からみづらそうなブレスにもこの調子だったのだろうか。
さらにその評価が「面白い」って?
なんだか色々すごい。
「ブレス、喋ったんですか?」
この双子先輩に尊敬の念すら抱きつつ、いちばんの疑問を聞くと……
「いいやー」
「まさかー」
……ふたりは、そろって首を横に振った。
「……」
「あっ、ものっそい冷たい視線。会話はしたでっ。ウソやないっ」
「そや、捏造したわけやないで! 芸人魂に誓ってヤラセは一切しとらんぞっ」
「喋らない相手と、どうして会話できんだよ」
思わず敬語を忘れてぼやくと、二人は意味ありげに顔を見合わせて、ししし、と笑った。
「口を割らんなら、なぁ」
「カラダに聞くしかないやろー」
「下ネタかよっ!!」
その手の話が嫌いなヘヴンリィは、勢い良くツッコミで斬り捨て、二人に背を向けて歩き出した。
必要な分の薬草は、もう十分摘んだ。そんな展開の話をされるぐらいなら、街に帰って施薬院にでも行くほうがまだマシだ。
「あぁイヤ嘘うそっ、怒らんといてっ。もう下ネタ言わへんからっ」
「そや、待ってテンちゃんっ。本当のこと言うたるから。 実は……、俺ら、サイコメトラーやねん」
「……サイコメトラー?」
真面目な顔でそういった二人に、街への帰路へと向けた足を止めて、ヘヴンリィは振り返った。
色素は違えど、鏡写しのごとく、これだけ造作が似ている双子は珍しい。
不思議な力を持っていても、ああそうかと納得できるような雰囲気がこのふたりにはあった。
「ん、そうや。よーく見たってなー」
振り向いたヘヴンリィに嬉しそうな笑みを見せると、二人は縦に並んだ。エンジを前、ミズキを後ろ。
そして、
「幽体離脱ー」
エンジの後ろから、おどろおどろしくのぞいてそんな台詞を口にするミズキ。
「某芸人のパクリじゃねーかよ! なにがサイコメトラーだっ、ざけんな!」
ちょっと期待していた自分が恥ずかしくなり、ヘヴンリィは双子に向けておもいっきり怒鳴った。
しかし、双子はふたたび横に並ぶと、そんな彼を見て満足そうに笑う。
「なんや、キレのいいツッコミもできるやないか」
「そやな、今の勢いはええ感じやったぞ。少しは、気ぃほぐれたかな?」
「……っ!?」
年長者ゆえか、優しさを含んだその二人の声に、ヘヴンリィはぎくりとした。
一軍にトラブルがあったのを知って、様子見や、機嫌の緩和にきたということなのか。
そうだ。よく考えてみれば、今この丘に自分がいることを、この双子が知りえるはずがない。
「……っ、なんだ、ブレスの差し金かよ……?」
自分の前はブレスだと言っていた。敬語をやめて、警戒を強めつつヘヴンリィは二人に問う。
「ちゃうわ、誤解やテンちゃん。ここにいるって教えてくれたのは、ブレっちやけどな」
「そや。君は一人目が誰か、聞いてへんよな?」
「……誰なんだよ?」
問いながらも、ヘヴンリィの予想は99%確定していた。
おおかた、あの容姿も気配りも爽やかにパーフェクトな男前ソードマン、リザンなのだろうと。
しかし。
にやり、と笑うふたりの笑みは、まさに悪戯を仕掛ける猫のようだった。
「ロッたんや」
「……ミズキ、やはり俺はフレりんのがいいと思うんけど」
「いーや、絶対ロッたんやって」
「そーか、勝手にしいや。俺はフレりんて呼ぶからな」
……『フレりん』、『ロッたん』。
ふたつの渾名から推測されるのは……ヘヴンリィが一番嫌いな、あいつ。
「……お嬢様かよ」
憎々しげに、ヘヴンリィは吐き捨てた。
「『お嬢様』はないやろ、テンちゃん。それ、相当なトラウマらしいで。フレりんは」
「知るか」
歩み寄りながら言ったエンジの苦笑に、ヘヴンリィはぷいとそっぽを向く。
あんな最低馬鹿が傷つこうがトラウマだろうが、知ったことじゃない。
それに、そんなに嫌ならば肩に届くくらいのあの木苺の髪を切るとか、女に間違われないような努力をすべきだろうと思う。
努力せずに反抗だけするなど、甘すぎる。愚の骨頂だ。
「えらいヘコんで馬に乗っとったのを、俺らが見かけてな。色々聞いたんや。で、初!樹海探索☆インタビューを開始したってワケ」
「へぇ」
ミズキの声は同情的だったが、ヘヴンリィは冷淡に返事を返した。
へこんで当たり前だ。
めちゃくちゃな戦い方に、自分に対しての暴言。
多少反省するくらいは、人として当然だろう。
(つーか、「馬に乗って」とはまた……優雅なご趣味だな、おい)
ヘヴンリィは胸中で毒づいた。
馬一頭の維持も、今のエトリアでは困難だというのに。
おおかた、相当な仕送りでも貰っているのだろう。これだから騎士様のボンボンは嫌だ。
「……テンちゃん。 ロッたんは確かに世間知らずやけど、根はめっちゃいい子やぞ」
先ほどまでの軽い口調を一転、真剣な声音でミズキは言う。
しかし、そのくらいでヘヴンリィが嫌いな奴:第一位の座は揺るがなかった。
「……どうだかな。それは貴方たちの価値観でしょう、先輩?」
紫水晶の瞳を細め、喧嘩を売るように敬語で毒づくヘヴンリィ。
「とげとげすんなや~、テンちゃん。なんでそんなに嫌いなん?」
しかし、双子は挑発に乗らなかった。柔らかい声で、微笑みながらエンジが問う。
「……」
その温和な流れに乗って口を開いてしまいそうになり、ヘヴンリィはちっ、とそんな自身に舌打ちをした。
理由は、ちゃんとある。無数にある。
けれど、それを他人に……しかもギルドの先輩に話すなど、彼としてはありえない。
自分の主観でしかない不満をぐちぐちと語るなど、許せない。卑怯だ。陰口のようなものだろう。
「……別にいいでしょう。一軍とは潜るし、メディックとしての役割は果たす。ほかに何か必要ですか」
不機嫌な顔を保ったヘヴンリィが冷たい声でそう告げる。自分の言葉がフレアロットの暴言と似ている気がして、心の中で自嘲した。
(……そう、「メディックなんだから」傷は治してやるさ。役割として、な)
ヘヴンリィのすさんだ気配をまとった声と瞳に、双子は困ったように笑った。
「……そか。しゃあないなぁ。 ほな、詳細は聞かへんよ」
「ああ、けど、あんま思いつめんといてな。 テンちゃんも、可愛い後輩なんやから」
その言葉に、びく、と心の奥がひきつった。
言葉の終わりにぽんと肩を叩こうとしたミズキの手を、ばし、と強い力で叩きおとし拒絶する。
突然のことに、双子は目を丸くしていた。
「……――っ……、…………すいません。 ……失礼します」
一瞬苦しそうに逡巡し、ヘヴンリィは顔をしかめたまま頭を下げて謝る。そして、双子の顔を見ぬまま背を向けて早足で街へと歩き出す。
……あの二人は悪い人じゃない。さっきのは普通の行動だ。その言葉にも悪意はない。わかっている。わかってはいる……はずなのだが……
「『可愛い』後輩」……その言葉は……、嫌だ。 聞きたく、ない。
自分はもう、可愛いなどと言われないようにしている。そんな目で見られないように、そんな輩になめられないように、対策をしている。不機嫌な顔で、黒い服とアクセサリーで、おとなしくない髪型で。
……自分の容姿は好きだ。両親に貰ったものだし、整っているのは悪いことじゃない。
が、他人の目という観点から言えば、同じくらいに嫌いでもあった。
……娘に間違われるのが嫌だというフレアロットの気持ちが、わからないわけではない。
だからこそ、自分はあいつが嫌いだ。嫌ならなんとかすればいい。それを、咆えるばかりで自分でどうにかしようとしていない。
甘いのだ。なにもかもが。
(……ああ、もう、ふざけんじゃねえ…!)
何に苛ついているのか。わからないくらい、ただひたすらに腹が立つ。
ぐちゃぐちゃになった行き場のない思考を抱えながら、不機嫌な顔でヘヴンリィはただひたすらにエトリアの街へと歩を進めた。