TURN2 「聖騎士の後悔」 零式彗星/千年王国
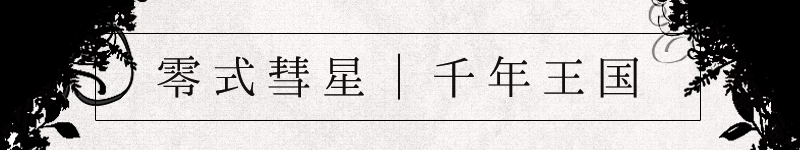
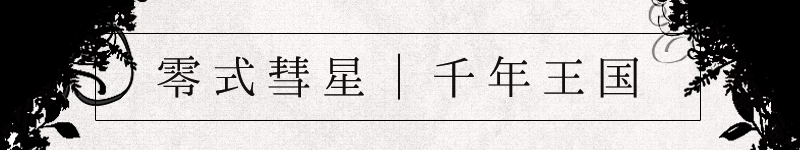
漆黒の剣を、一閃。
標的を斬るときの手ごたえは、その剣のように黒い。
(……嫌だな)
勢いのままにくるりと身を翻し、フレアロットは苦さをおぼえた。その一呼吸に、討ち損じた殺気への反応がわずかに遅れる。
「……っ!」
死角だった右後ろ。狙われた頭部を咄嗟にかばった左腕の盾はほんの少し遅かった。運悪く、鎧の隙間の二の腕を爪で切り裂かれる。
浅い痛みだったが、意識が手にした剣からそれないように息を止める。
痛みに耐えるのは得意ではないが、それを補う反応力には自信がある。即座に身体をひねりつつ、再度飛びかかってきた標的へと切っ先をはしらせた。
この距離では、先刻のように横には振りぬけない。細身の黒い長剣を右真横にまっすぐ突き刺し、即座に引き抜く。
叫びすら紡がず、腹部を貫かれた白灰色の狼――フォレストウルフが緑の草むらにどさりと崩れた。
(はあ……)
鋭い気配が消えたのを感じ、止めていた息を大きく吐き出す。無意識のうちに、その黒い細剣を腰の鞘へと収めていた。
この黒い剣……スズさんより譲り受けた「ドヴェルグの魔剣」に血曇りがついているのを、フレアロットは見たことがない。
羽ばたきカブトの堅い甲羅やボールアニマルの硬質な皮に刃を立てても、刃こぼれどころかやすやすと切り裂いてしまうこの剣は、業物だが得体が知れなくもある。
この剣をはじめて手渡されたときには心躍ったけれど、できればあまり柄を握っていたくない、というのが今の正直な感想だった。
「お疲れ、フレアロット」
ぽんと軽く胸当ての背を叩かれて振り返ると、メンバーのひとり、ソードマンのリザンさんが爽やかに微笑んでいた。あたたかな笑顔に、ふっと心が軽くなる。軽く頭を下げ、僕も笑顔を返した。
濃紺に墨をさしたような影青の髪に、穏やかな深い焦げ茶の瞳。均整の取れた長身と精悍な顔立ちをしているが、整った容姿にも関わらず気取ったところはまるでない。
ソードマンにも関わらず、はじめて樹海にもぐった今日、彼はまだ一度も剣を振るっていない。 その理由は僕が先に魔物を片付けているからだ。
しかし僕にかけた「お疲れ」の声には、皮肉の影が微塵もない。
ともすると血の気の多いソードマンという職業においても、ほんとうに彼は人格者だと思う。リザンさんでなければ、きっと僕は嫌味や罵倒を受けていただろう。
24歳にしてこの落ち着きはらった物腰は、尊敬に値する。とても格好いいひとだ。
メンバーの中で唯一、彼と組めたことだけは良かったと思っていた。
……他のメンバーは、お世辞にも良かったとは言えないけれど。
リザンさんの後方で、あの青く神秘的な弓をぞんざいに背にもどすレンジャー、ブレス。
流れるような金糸の長髪をかきあげ、怜悧なアイスブルーの眼で周囲をうかがっている。
リザンさんよりさらに長身なのでよく見渡せるんだろう。歳は僕よりも少し上か。まあ、別にいくつでもいいけど。
……そう、金髪碧眼。 しかも、元一軍は彼をリーダーに指名している。
このレンジャーと顔を合わせたとき僕は本気で一軍辞退を申し出たが、アキラさんに「君はなんのためにココに来たんだっけ?」と、勲章をぶらさげてにこりと微笑まれてしまったので仕方がない……。
さらに、会ってから3日、このレンジャーの声を僕は一度も聞いていない。
あいさつはおろか、名乗りすらしなかった。仮にもリーダーだというのにどういうつもりなのかは知らないが、失礼にも程がある。
放つ矢の威力はすさまじいが、アーチドロワー自体が逸品なので果たして実力なのかどうか。とりあえず金髪碧眼でさらに無礼だという時点で、僕の中では最低だ。
僕の後ろで存在感希薄に佇んでいるアルケミスト、シェズ。
狼のようなばさばさの長い黒髪からのぞく柘榴色の大きな瞳も、レンジャーと同じように周囲をうかがっていた。ただし、ぼーっと。単に辺りを観察しているだけなのかもしれない。
僕よりも小柄な上に細い体躯で、ブルーブラックのローブからのぞくごつい篭手が重そうだ。はじめに見たときは女の子かと思った。
おそらく僕と同年代のこの少年もまた、絶望的に口数が少なかった。
初めて会ったときに、名乗りはした。握手もした。けれど、そのあとは一言も喋らなかった。
例外は、樹海にもぐるときに僕たちの並び順を告げたリザンさんにひとこと、「イエス、サー」と言ったのみ。他は、話しかけても全く答えてくれない。むしろ、無視。
元は軍人なのかもしれないが、なにも無視することはないと思う。
リザンさん同様、この少年もまだ出番がない。ほんとうに術式が使えるのかすら疑いたくなってくる。
そして、一番最悪なのが残る一人だった。
「おい」
不機嫌な声が、ぐいっと左腕を引いた。
痛っ、と小さく声を上げたフレアロットに、かけられたのは皮肉と舌打ち。
「さっさと腕貸しやがれ。手間かけさせんじゃねえよ、『お嬢様』」
彼が娘と間違われるのを嫌うことを知っていて『お嬢様』と呼んだのは、横でクリスタルロッドを振るっていたメディック、ヘヴンリィ。
常に不機嫌そうな表情で甘い顔立ちを台無しにし、オールバックの髪型と無数の黒いアクセサリーで純白の豪奢なエンジェルローブを台無しにしている。
そしてこのメディックを一番台無しにしているのは、その毒舌。
「……貴様っ、僕を愚弄するのもいいかげんに……!」
きっと睨みつけて言い返すフレアロットだが、冷たく光る紫水晶の瞳に斬り捨てられる。
「口だけは達者ですか、『お嬢様』? 黙って治療されることすら出来ねえのかよ」
暖かみなど微塵もない声で毒づきながら、しかしヘヴンリィのその手は迅速で無駄がなかった。
いつ取り出したのか左手のガーゼで血を拭いながら、右手に持つ蓋の開いた試験管に、ぱあっと柔らかい光が瞬く。雛鳥のような優しい温度のその光が傷口をつつむと、もう傷は完全に癒えているのだ。
フレアロットが知る限りでは、こんな凄腕の医術式は見たことがない。
ひとくちにメディックといっても、その治癒法は千差万別である。フレアロットは医術式が苦手だったためヘヴンリィの医術式の原理まではわからないが、とにかくすごいことだけはわかる。
けれど。
腕を離して開口一番、フレアロットに告げた言葉は――
「怪我すんじゃねえよお前、めんどくせーんだよ」
心底嫌そうに吐き捨てられては、ありがたいはずの治療も全く嬉しくなかった。
一番に前線へ駆けて剣をふるう僕は、そのぶん幾度か手傷を負っていた。その傷は浅いものばかりだったが、ヘヴンリィはすぐにその傷を治していた。ただし、毎回、不機嫌と皮肉つきで。
(なんでこんなやつがメディックなんだ……)
『お嬢様』呼ばわりされた上に、めんどくさいとまで言われた僕の苛立ちは限界だった。
これは言っちゃいけないんだと頭では分かっているのだが……、もう、止められなかった。
「……僕は、治してくれなんて頼んでない」
くるりと背を向けて道の先へ歩を進めようとしていたヘヴンリィが、僕のその一言に振り向く。
「……あ?」
ものすごく剣呑に。
ずっと言葉の暴力を行使していたのは、そっちだろう。そんな瞳をするのは筋違いだ。
ほんの少し見上げて、睨み返した。空気がはりつめる。
ヘヴンリィだけでなく、他の三人も僕とヘヴンリィに目を向けて足を止めた。
「今までの傷は全部致命傷じゃない。 頼まれもしないのに文句を言いながら治していたのは貴方自身だろう? 面倒なら、あの程度の傷はもう治してくれなくてもいい」
きっぱりと、怒りに細められた紫水晶の瞳を見て、言い放つ。
形だけは無駄に良いヘヴンリィの唇が、無意識なのだろうが、怒りにふるふると震えていた。
「……てめぇ……っ!!」
低い唸り声も、鮮烈な怒りの表れなんだろう。
けど、僕だって心底腹が立っているんだ。
僕だけが怪我しているのは確かだけど、逆に言えばほかの誰も怪我をしていない。僕は僕なりにパラディンとしての役割を果たしているだけだ。
それなのに、なんで文句を言われなきゃならないんだ。
……っていうかさ……、
「貴方はメディックなんだろう」
そう、傷を治すのが仕事なんじゃないか。
「……」
なら、メンバーである僕を憎々しげに睨む必要なんてないだろう?
むしろ、僕は君に仕事を提供してるんじゃないか。
「メディックなんだから、傷を治すのは当然だろう?」
息をのむ気配。……それはヘヴンリィだけではなく、他の三人も同様だった。
けど、僕は間違ってない。
医術式を行使しないまま、最初の探索を終えるよりはいいと思う。
初めて樹海に潜っても出番のないリザンさんやシェズより、僕のおかげで君は恵まれているはずだ。
「ふざけんじゃねえぞ、てめぇっ……!!」
なのに、なぜ僕は襟首を捕まれて罵倒されなきゃいけないんだ?
ふざけんなって言いたいのは僕のほうだ。
さらに言いつのろうとした、そのとき。
「やめろ。フレアロット、ヘヴンリィ」
僕が言葉を紡ぐよりも一瞬先に静かな声を響かせたのは、リザンさんだった。
「今日はもう帰ろう。アリアドネの糸を使って街へ帰る。いいな?」
僕と、このメディックに一応聞いた形だけど、その響きは有無を言わさぬもの。
「はい」
僕は即座に頷いた。
リザンさんにまで反論する理由はない。それに、腹が立ってばかりで精神的にすごく疲れた。
それだけは、ヘヴンリィも同様のようだった。
「……ああ」
僕の襟首をつかむ力を解き、手を離す。こちらを見てもいたくないというように、ざっと背を向けて離れた。腹が立ったままの僕としても、この行動はありがたい。
開放された襟ぐりを直しながら、僕は大きく息をひとつ。
三人はヘヴンリィにも僕にも、何も言わなかった。
前置きもなく唐突にレンジャーが起動させたアリアドネの糸の空間転移効果によって、ふわりと視界がくらんだ。身体が重力に吹き飛ばされるような感覚につつまれる。
きもちわるい、と思った瞬間に、僕たち5人は樹海の入り口に立っていた。
誰ともなく、言葉もなく散り散りにエトリアの街へと戻っていく。
このあとも5人で行動なんてできそうになかった僕は、ほっとしてその場に立ち尽くした。
美しい緑と石壁が織り成す、綺麗な門とその下り階段を見て、心が沈む。
……5時間前、ここへ来た朝の8時には、こんなふうに探索を終えるなんて欠片も思っていなかった。
苛立ちに、寂しさと落胆が重なって、僕はため息をついた。
故郷から夢見てきた樹海探索の初日は、ひたすら腹が立ったまま、幕を閉じた。
こんなはずじゃ、なかったのに。
ぐちゃぐちゃになった思考の中で、鮮明に頭に響く一言。
最悪だ。
後には引けないけれど、最悪だ……!!
ぎり、と苦く奥歯をかんで、僕は最悪な樹海に背を向けた。