TURN1 「聖騎士の受難」 零式彗星/千年王国
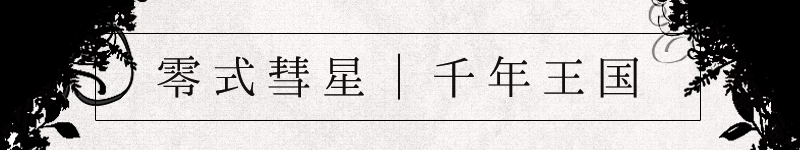
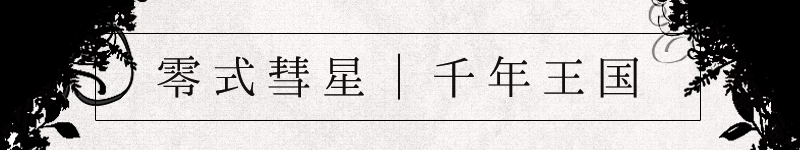
僕は、目の前に広がる光景に胸を衝かれた。 捨ててきた城塞都市とは比べようもなく小さな街と、その只中に厳かにそびえたつ大樹。 幾多の草原を、森林を、山脈を愛馬ファルシオンと共に駆けてここまで来たが、こんな樹を僕は見たことがない。 微妙に異なる緑の色彩が、天を愛でるように広げた枝先からこぼれ、豊かで涼やかな葉影は街を包み込み優しく落とされている。 思わず祈りを捧げたいほどに大きなその存在は、ずっと夢見ていたものよりもすばらしかった。 (――ついにエトリアに着いた!) ここから、僕の冒険者としての一歩が始まるのだ。 あの大いなる樹下に眠る「世界樹の迷宮」に挑み、そして……「エトリアの勲章」をこの手にするための、第一歩が。 それは途方もなく危険で無謀だというけれど、だからこそ必ず持ち帰り、そして僕を嘲ってきたかつての同郷の者達に知らしめるのだ。 僕がどれほど強く、勇敢であるかを。 高揚感のままに、僕――フレアロット・ラングスティールは、ファルシオンにひとつ早駆けの鞭をたたいた。 しかし。 「新規ギルドはもう受け付けていないぜ」 「そ、そんなぁ!」 「世界樹の迷宮」を探索する冒険者が、探索を許可するという証の「登録」をしなくてはいけない場所『冒険者ギルド』で、ギルドを管理するギルド長のオッサ……いや、年季の入った眼帯の男は、僕のまっとうな申請を一蹴した。 朝方という時間のせいか、5~6人が座れるような大きいテーブルがいくつか並ぶ広めの施設の割に人影はまばらだ。僕の叫び声がよく通ってしまったが、振り返る人も少なくて助かる。 迷宮探索をするには、冒険者としての色々な書類の登録に加え「ギルド」という冒険者の所属を登録申請するという規則がある。そのため、既に組まれているギルドのパーティへ参加希望を出すか、待機状態としてスカウトされるのを待つか、あるいは新しくギルドを起さなければいけないという話を聞いていた。 僕は、自身でギルドを立ち上げ、共に戦う仲間を一から集めるつもりだった。 なのに、オッサン……い、いや、初老一歩手前の眼帯野郎は、頑として首を縦に振らない。 「ギルドの登録数が多すぎんだよ」 にべもない返答。 どうやら、僕がここエトリアにたどり着くのが遅かったようである。 でも、僕としては最短の時間でここに来たのに…… 歯噛みしてうつむく僕に、付け足すようにオッサンが呟く。 「ここ数日で、やけっぱちで新しいギルドの登録をする新参者が後を断たねぇんだ。あの迷宮の謎を解いたギルドに、加入するのを断られた奴等がな」 そうして駆け出しの新人ばかりで構成されたギルドのパーティが勢いのみで迷宮へもぐり、結果、その大半が帰ってこないという。だから執政院との条約で、現在新規ギルドの申請を断っている。 そんな説明を受けたが、はいそうですかと納得なんてできなかった。 人の下に見られるのが嫌で故郷を飛び出してきたのに、今居るギルドのリーダーの下に在籍するなんて。 だが、故郷の奴らに目に物見せてやるために僕はここまで来たのだ。ならば、一時人の下につくという悔しさも、乗り越えなければならないか……。 悔しさにうつむいている僕に、オッサンは一つ深いため息を吐くと、ギルドの管理帳を開いた。 「これが現在登録されているギルドだ。パラディンを必要とするパーティは多い。希望を出すなら慎重にするんだな」 「………………はい……!」 苦い思いを飲み込み、僕はその管理帳を隅から隅まで熟読した。 「……あー、くっそー……! ふっざけんなぁ……」 日もまだ沈まぬ、太陽が傾いてきた程度の昼間。 「ご婦人っ! おかわりください!」 僕は、半月前に覚えたばかりの酒をかっくらっていた。 「もう止めたほうがいいんじゃないの?」 『金鹿の酒場』、ここエトリアの街で冒険者を相手に酒場と情報屋を営む女性が、困ったような微笑を浮かべながらも僕に酒を注いだグラスを差し出す。客がまばらな時間のため、カウンターに座る僕の話し相手となっていた。 「パラディンなら、欲しがるギルドはいくらでもあるわよ? 剣を使う人はたいていソードマンになっちゃうし、サドっ気があるひとはダークハンターになっちゃうし。パラディンは不足しているのよ」 優しい目で、僕を諭すように話す。たおやかで品のある美人な方だが、泣きボクロと胸元の開いた衣服の妖艶さは目のやり場に困った。意識しないようにと思ってはいるけれど、視界に入るとどうしても動揺してしまう。 見ないように、僕はテーブルに突っ伏す。そして酒の勢いか、独白めいた言葉が知らず知らずのうちに口をついた。 「でも、嫌なんです……金髪は嫌いなんですっ!」 「そう……」 婦人のいたわるような声が、むしろ痛く感じた。……そう、同情されるのも、逆に蔑まれるのも、ありふれた反応だ。 僕には金髪に対してトラウマがあった。18歳まで過ごしてきた、故郷――セイクリッド・クルスの血筋誉れ高いパラディン達は、金髪碧眼に白い肌のものばかりだったのだ。その肌の色、瞳の色と髪の色は、彼らの純血たる誉れでもある。 それに反して僕の容姿は、周囲とも二人の兄とも違っていた。ラズベリー色の「木苺の髪」と、日焼けではなく生まれついた「褐色の肌」。瞳の色はエメラルドのような緑色だ。 金髪なんて。白い肌なんて。碧眼なんて――。 そんなものを持った奴らは、誰も僕の実力を見てくれない。なのに…… 「なんで、ここまで来て金髪見なきゃならないんだよっ……あー、もう」 突っ伏したまま唸ってくらっとしたのは、怒りか酒のせいか。おそらくは両方。 何の因果か、ギルドリーダーは金髪碧眼ばかりだった。 この期に及んで共に迷宮へ潜るパーティのリーダーが金髪だなんて、考えられない。 小一時間管理帳を睨んだあげく、結局どのギルドに属したいとも言えなかった僕は、こうしてヤケ酒をかっくらっていた。 身を起こしてまたひとくちグラスに口をつけたとき、からころと来客を告げる扉のベルが背後とおくで鳴った。 「お久しぶりです、マダム」 低音の女性とも、優男とも取れる若い声が耳を打つ。砕けすぎず、それでいてすこしだけユーモアを含んだ響きが涼やかだ。 僕は振り返らずに、グラスを傾けたまま耳を向ける。 振り返った先が男性の場合、僕を娘と勘違いして寄ってくることがあるのだ。旅路の酒場で、何度かそんな失礼な輩を叩きのめしてきた。今の気分で面倒なんて心底ゴメンだ。 「あら。本当におひさしぶりね、アキラ。時の人は違うわね」 婦人がにこりと笑みを返すが、とがめるように後半を強調する。顔馴染みなのだろうな、と僕は思った。 「相変わらずきっついなあ。カウンター、いい?」 その声が近づいてきているというのに、足音も気配も入ってきたときから全くない。おそらく、相当に腕の立つ人だ。 「そうね……いいかしら?」 「はい。僕は構いません」 「それじゃ、失礼します。っと」 椅子ひとつあけた左側へ座ったその人をちらと見て、僕は息を呑んだ。 つばの広い帽子に、濃い蜂蜜色の長髪が流れる。すらりと高い背に、敏捷さを優先する軽装な防具と、右目に黒い眼帯。声や口調のみならず、容姿でも男性か女性か、よくわからない。背にした弓はレンジャーであることを伺わせた。綺麗なひとではあるが、しかし、息を呑んだのはその弓。 「あ、アーチドロワー……!」 青く神秘的なその弓は、海王と呼ばれる伝説の魔物コロトラングルの「永遠に凍りつく骨」のみでしか作られない。希少価値、芸術性、その性能のどれをとっても一級品であると故郷の文献に記されていた。 遠く離れた都市の文献に載っているほどの弓を、こんなところで、しかもこんな間近で見られるなんて……!! 「お、この弓知ってるの?」 僕へレンジャーさんが向き直るが、僕は目を合わせられずこくこくと頷いた。うう、ダメだ。失礼とはわかっているけど、肩越しにのぞく、あの青い弓から目が離せない。 「そっか、こいつの価値がわかるなんて嬉しいなぁ。君、どこの所属?」 「はいっ、ここエトリアに来たばかりなので、特に所属はないですっ」 冒険者ギルドで唸ったあげく登録しませんでした、というのは滞在時間に入れません。だから嘘じゃないです。 生きてきた中で五本の指に入るくらい目を輝かせていた僕に、よし、とレンジャーさんは悪戯っぽくにやりと笑った。 「君、『グランドクロス』の次期一軍パラディンに決定」 ……え。この人のギルドに、勧誘されている? 確かにこの弓を四六時中見ていられるというのは、とても魅力的だけれども。 けれど、僕の記憶が間違っていなければ『グランドクロス』という名のギルドは、管理帳になかったはず。それよりも、「次期一軍」とは? いったい、何を言っているのだろう。 きょとんとしている僕と対照的に、カウンター越しの婦人は心底驚いたというようにおろおろしていた。 「え、ええ? アキラ、そんなに簡単に決めていいの。ずっと探していた貴方の後継でしょう?」 さわやかな笑顔で、無言の肯定をするレンジャー、アキラさん。 とても腕の立ちそうな人。ものすごい武器を持つ人。管理帳になかったギルド。「次期一軍パラディン」。「簡単に決めていいの」。「ずっと探していた貴方の後継」。 冒険者ギルドのオッサンの眼帯と、目の前の眼帯がだぶる。 『ここ数日で、やけっぱちで新しいギルドの登録をする新参者が後を断たねぇんだ。あの迷宮の謎を解いたギルドに、加入するのを断られた奴等がな』 ……そういう、ことか。 すべての手掛かりをつなげ終えた僕は、目から輝きがすっと消える感覚を感じた。 「いやです」 「え?」 意外な返答だったのか、僕の声が小さかったのか。笑顔のまま聞き返すアキラさんに、僕はきっぱりと言った。 「嫌だと、言っています。あなたの後継者になど、なりたくありません」 できるだけ、拒絶の意を込めるようにまっすぐ、片方だけのぞく左目を見て。 左目は栗色だった。すこし安心したけれど……でも、そんなこと問題じゃない。 僕が失望したのも、ヤケ酒していたのも、おそらくこの人とその仲間の「迷宮の謎を解いたギルド」のせい。 なのに、ヤケ酒の現場にひょっこり現れて、僕を後継にするだと? 勝手にもほどがある。 顔をカウンターの先の酒のビン達へ向けて、グラスの酒をひとくち。以後無視だ。絶対拒絶してやる。 「でも、そう決めちゃったんだけどなぁ」 「それは貴方の都合です。僕には関係ありません」 諦めずに言い募る勧誘をにべもなく断った、はずなのだが。 「そう? はいと言ってくれれば、これも君に譲るよ?」 アキラさんの笑みを含んだ口調は、しかし崩れない。厳かな動作で僕の前に掲げたのは、見事な金細工に上質な宝石とビロードをあしらった美しい勲章だった。 ……嘘だろう。 視界にそれを認めて、僕の思考が止まる。ごくりと、つばをのんだ音がやけに頭に響いた。 「エトリアの勲章」 凍りついた僕の心を読み取ったかのように、静かにその名を告げて目を細める。 「聖騎士の間で名誉の証とされている、誉れある勲章の一つ。コレを目指してエトリアに来るパラディン、多いんだよね」 ……なぜ、遠く離れた都市の文献に載っているほどの勲章を……こんなところで、しかもこんな間近で見られるなんて。 先刻の弓と似かよった感想を、だが、先刻の憧れとは正反対の苦々しさをもって、僕は思った。 「君がただ一言、「はい」と言えば手に入るよ。いとも簡単にね」 黙ったままの僕をのぞきこみ、にっこりと笑う。嫌味のない、爽やかすぎるその笑顔はむしろ痛烈な皮肉だ。 苦労してここまで来て、酒場でヤケ酒していただけで、エトリアの勲章が「いとも簡単に手に入る」だって? そんなの、嘘だ。欺きだ。こんなことで手に入れたとしても、それは僕の力の証じゃない。僕はそんなものが欲くてここへ来たわけじゃない。 しかし僕は今、そんな「ただのモノ」で釣れるパラディンだと思われている? 叩き落されるような失望感。かあっと、頭に血がのぼった。 「ふ、ざけるなっ……!!」 グラスをカウンターへ乱暴に叩きつけ、ぎゅっと握った右の拳を振りかぶった。 瞬間、レンジャーの皮手袋に包まれたしなやかな指が、ここん、とカウンターを叩く。 一秒にも満たないほんの一瞬、僕の意識がそれた。次の瞬間、 「うわあっ!?」 伸ばした拳ごと右腕をすっと払われ、身を乗り出していた僕はバランスを崩す。見事に転び、酒場の木床に倒れこむ ……はずだった。しかし衝撃は無く、羽でくるまれるかのようにやわらかく、誰かが僕の背中を受け止めた。 「いい加減にしなさい。アキラ」 背から、凛とした女性の声。女性? 後ろに顔を向けると、眉を思いっきり吊り上げたプラチナブロンドのひとがアキラさんを睨みつけていた。 「お、ナイスフォロー。スズ姉」 「何がナイスフォローよ。勧誘してるんでしょ、なのにその子をいじめてどうするの。意地が悪いわよ」 「いやぁ、あんまりまっすぐな目をしてるからつい」 「つい、ってね……、ああ、もういいわ。もうあんたなんか知らない」 その瞳に負けず劣らず烈火のような非難を言い放つスズ姉と呼ばれたその人は背の手を離し、僕の左へ移動してアキラさんの隣に並んだ。 紺色の長いコートを翻し、うちの馬鹿が意地悪言ってごめんね、と、先ほどとは一変した暖かい声で僕に非礼を詫びる。 「私はスズ。ギルド『グランドクロス』のパラディンよ。この馬鹿、アキラと同じパーティにいたの。今は、引退してしまったけれどね」 手袋をはずして差し出された手を、握手で返す。名乗ると、「西方系ね。いい名前だわ」と微笑んだ。そして、一つため息をつくと、険しい顔で眉を寄せて話しはじめた。 「自分が苦労しないで手に入れる勲章なんて、意味が無いわよね。でも、そう思ってくれるパラディンは今まで居なかったのよ。勲章さえ手にできればいいって人ばかりで。幻滅よね。こんな奴らでも名乗れる『パラディン』って一体何なの、って思ったわ」 心底嫌そうに吐き棄て、でも、と呟く。綺麗に切りそろえられたボブカットの髪を揺らし、花が咲くように笑った。 「貴方はエトリアの勲章を前に、そんなものいらないって怒ってくれた。すごく嬉しいわ。同じパラディンとして」 表情の豊かなひとだなあ、と思いながら、僕はどう答えてよいかわからず曖昧にうなずいた。 細められた目は、紫がかったアイスブルー。金髪碧眼だ。けれど、嫌な気持ちはなかった。 衝撃を完璧に殺して僕を受け止めたあの手は、僕が知る誰よりも優れたパラディンの手だ。仲間を守る盾として、攻撃を受けることに慣れている者だからこそできること。 その人が、僕を賞賛してくれている。僕と対等になって、微笑んでくれている。……すごいことだ。 「だから、貴方が後任のパラディンになってくれると嬉しいんだけど……。私たちが辿り着けていない迷宮の深遠へ、貴方なら行けると思うの。よく考えて、決めてみて。考えた上でやっぱり嫌だと貴方が言うなら、諦めるわ」 「それに、僕のあとを継がなきゃ勲章は手に入れられないけどね。最初に迷宮の謎を解いた人にしか与えられないみたいだし、これ」 「アキラ、いい加減にしなさい!」 スズさんが怒る。だが、アキラさんの言うことも重要な要素ではあった。 エトリアの勲章は、手にしたい。けれど、後を継ぐというだけで手に入るのは嫌だ。 ならば、僕の答えは一つしかない。 「僕は…… 僕は、貴方達よりも、強くなりたい」 パラディンとしてスズさんの腕を見た今、それが途方も無い思いだとはわかっていた。けれど、それでも僕は、必死になって思いを声に出した。 二人のまっすぐな視線に向かいあい、もういちど確認するようにゆっくりと誓う。 「貴方達よりも強くなって、迷宮のもっと深いところへいけたなら…… その時、エトリアの勲章をお受けしたいと思います」 僕が言い切ると、二人は顔を見合わせて満面の笑みを浮かべた。 「よっしゃあああ!」 「やっといいコが入ったわね! これで後継者が揃ったわ!」 ぱちん、と上機嫌でハイタッチなどしている。 え、えっと……? 「いやぁ、貴方の悪役っぷりは相当だったわよアキラ。勲章のくだりはあっちで聞いてて、半分剣を抜きかけたわ」 あっち? アキラさんが入ってくる前からスズさんはここにいたのか? 「ここで刃傷沙汰は勘弁してよスズ姉~。お世話になってる『金鹿の酒場』さまに申し訳が立たないじゃん」 「そうねえ、彼に最初に目をつけたのは私なのだから、大きな騒ぎは勘弁して欲しいわね」 にこにこと、カウンターの婦人までもが同意する。 え、それって…… 「あ、あの……」 おずおずと手を上げる僕に、ん?と三人が目を向ける。 「僕、はめられたんですか……?」 「そゆこと」 「ごめんね、ほんとに」 「見込みありそうなパラディンが来たってギルド長から聞いていたから、あなたに違いないと思って彼らへ連絡したの。ごめんなさいね」 謝る二人と、補足する婦人の言葉。 ギルド長……あのオッサンか! 見込みがありそうだと思ってくれたのは嬉しいが、これってどうなんだ…… 「うん、でも実際会ってみてホントにいいと思ったわよ。うんうん」 「ええ。ヤケ酒ぶりは置いておいてね」 「いや、酒でストレス解消できるのは長所だぜ? パラディンで飲めるのは大事だよ。なぁスズ姉」 「なんでそこで私を強調するのよ」 固まっている僕をよそにひとしきり談笑し、ぽん、とスズさんが僕の左肩を叩く。 「じゃあ、さっそく冒険者ギルドで登録ね。フレアロット君」 「え、いや、でも」 にっこりとまぶしい笑顔でそう言われるが、僕はひきつった笑いを返すので精一杯だった。さっき出てきたばかりだし、酔っ払いが行くのもどうかと思うし。 何より、この怒涛の展開についていけなかった。決断したことを翻すつもりはないが、少し落ち着いて頭の中を整理する余裕が欲しかった。 しかし、目を細めたアキラさんにぽん、と右肩を叩かれる。 「善は急げって言うだろ?」 逃がさないぞ、という二人の意思表示がひしひしと伝わってくる。 ……というより、僕はこの二人から逃げられそうになかった。 「……はい……」 かくして、僕が「エトリアの勲章」を手にするための第一歩は……「エトリアの英雄」、アキラさんとスズさんに連行されて幕を開けた。 幸運といえば幸運だけど……これからどうなるんだろう、僕……。